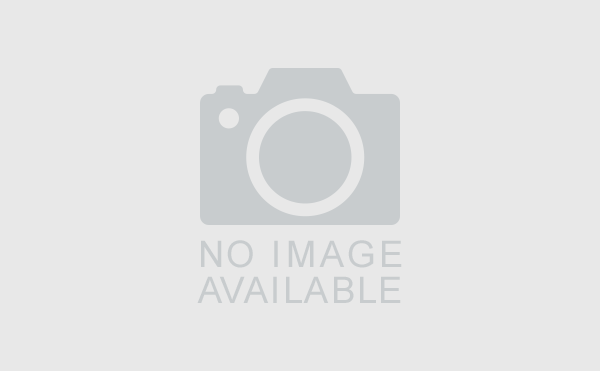PV展に行って感じたこと ― パネルからメンテナンスへ
昨日(9月18日)、幕張で開催されている**PV展(太陽光発電関連展示会)**に行ってきました。
毎年のように足を運んでいますが、今年は特に「出展内容の変化」に驚かされました。
以前はブースの多くをパネルメーカーが占めていたのですが、今は様変わり。目立っていたのはメンテナンス系の施工や、特に盗難防止に関する提案でした。相変わらず架台メーカーだけは出展されてましたが、それでもかなり減っているのでは?と感じました。
アルミケーブルへの移行と、それでも続く盗難

私のお客さんの多くはすでに銅線からアルミケーブルへ切り替えています。その結果、盗難被害は減ってきたと感じていたのですが、実際にはまだまだ件数は増えているようです。
どうやら最近は関東からさらに北へと盗難の範囲が広がっているとのこと。東北や北海道にはメガソーラーが多数あり、泥棒からすれば「狙いやすいターゲット」と見えるのかもしれません。
とはいえ、太陽光発電所の地中には銅線は今でも埋設されているため、一号柱と集電箱、キュービクルの周囲を掘れば“お宝”が眠っている状況。
ちなみに左の写真の写真中央部分の右にある銀の柱がケーブルを守るは箱です。
しかし、施工後盗難が減少したとうたっているほとんどの業者さんはアルミケーブルに変更してからの実績のようだ。
泥棒の心理は理解できませんが、一号柱や集電箱の周りだけいくら鎧で覆っても地中には銅線が無防備に通っている。(もちろん地中の銅線を多く業者さんもいましたが、その工事代金は馬鹿高いです。)そう考えると、一号柱や終電箱周りだけ覆っても、「被害は形を変えても結局続いていくのでは?」という気もしてしまいます。少しだけ切り取れる線の長さが減って泥棒の儲けが減るだけの話でしょう。でも電気事業者としての被害額は同じです。短くなった銅線をつなぎ合わせて一本にすることは難しい。
まずは買取業者の規制が先で、それまではアルミケーブルしかないと思うんだけど。ちょっと偏屈でしょうか。
中国製アルミケーブルの出展にびっくり
さらに驚いたのは、中国製のアルミケーブルが数多く出展されていたこと。一応日本の基準をクリアしているとは言っているが、古川製と同じように青い被覆で覆われており、「これって規格的に大丈夫なのか?」「パクリ?」と疑問が頭をよぎりました。もしかすると何かしらの違反に近いものも混ざっているのでは……と。慎重に導入する際は検討しないと。
小さくなった太陽光スペース
そんなことを考えながら会場を回っていると、以前と比べて太陽光関連の展示スペース自体が小さくなっていると感じました。90分あればたいがいのブースは見れました。
業界の成熟や再エネ政策の変化を映しているのかもしれませんね。
まとめ
今回のPV展で強く印象に残ったのは、
- 盗難防止の需要がますます増していること
- アルミケーブルが新たな主役になりつつあること
- 業界の重心が“発電”から“守る・維持する”へと移りつつあること
太陽光発電をめぐる環境は、確実に「次のステージ」に進んでいる。そんな実感を持った一日でした。