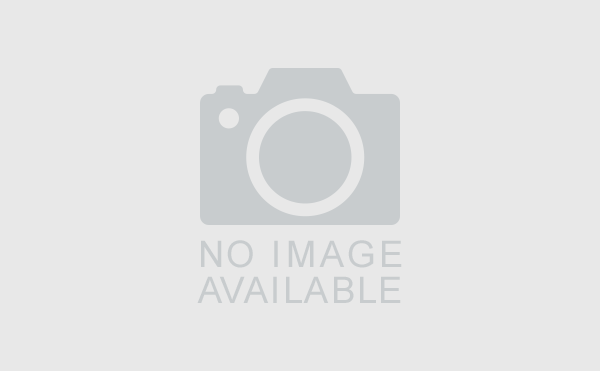太陽光発電所の除草作業に改善が求められています。

太陽光で発電された電気を家庭用や事業用に使えるように変換するPCS(パワーコンディショナ)という装置は、文字どおり発電所の中枢であり、電気を制御する「頭脳」でもある。
このPCSは常に電気が流れており、内部で熱を持つ。日常的には目立たないが、内部の配線が劣化したり、冷却ファンが止まったり、落雷があったりすると――火花を出すことがあるのだ。
では、そこに乾ききった草が積もっていたらどうなるか?
答えは簡単。火花が草に触れた瞬間に「ボッ」と火が上がる。夏の空気の乾燥、風の強さが加われば、一瞬で火は周囲のパネル、ケーブル、場合によっては隣の家、隣の山にまで広がる。
これが、PCSの周囲に枯れ草をためてはならない最大の理由である。
令和7年5月から施行された新しい技術基準でも、第3条で「人体に危害を及ぼし、物件に損傷を与えるおそれ」としてしっかりと明記されている。
解釈の中では、「PCSの周囲から可燃物を除去する」「防火用の砕石を敷く」「難燃性の防草シートを使う」などの対策が具体的に例示されている。
単に「やっておいた方がいい」というレベルではなく、「やらなければならない」とされている。
実際、こうした対策を怠ったことによる事故はすでに起きている。
2015年の宮崎県。PCSが異常発熱して火を吹き、周囲に積もっていた枯草に引火。架台は倒れ、ケーブルは焼き切れ、発電所全体が使い物にならなくなった。
2021年には静岡県で、夏の高温とファン故障が重なりPCSが過熱。下草に火が移り、あわや山火事という事態にまで発展した。
このような事例が増える中で、保険会社の目も厳しくなってきている。
「管理義務違反」と判断されれば、火災保険の適用対象から外される可能性すらある。
「いつ草刈りをしたか?」「写真で記録しているか?」「防草シートは難燃性か?」
そうしたことが保険金支払いの可否を分ける時代に入っている。
言ってしまえば、PCSの周りの雑草を刈るだけで、数百万円、あるいはそれ以上の損害を防げる可能性がある。
たった数分の草刈りが、発電所の命運を分ける。
PCSは、決して万能のロボットではない。人間の手で管理されてこそ、安全に働き続ける機械なのだ。
だから私は、こう強く訴えたい。
「PCSの周りに枯れ草を放置するな」と。
これは単なる美観や点検の問題ではない。人命と財産を守るための、最前線の行動である。
太陽は黙々と電気を生んでくれる。
だが、その裏に潜む「熱」と「火」のリスクを忘れてはならない。
太陽光発電という名の火を、人がどうコントロールするか――。
それが、これからの時代のオーナーに求められる責任です。
では、具体的にどうすればいいのか?次のような対策が考えられる。
PCS周辺に必要な火災・延焼防止対策
1. 枯草・落ち葉の除去(定期的な除草清掃)
- PCSの周囲1〜2m以内は、枯草・雑草・落ち葉を物理的に除去。
- 刈った草をそのまま放置すると、かえって可燃物が集積するため、必ず搬出処分。
- 可能であれば月1回ペース、特に夏前・秋口(乾燥期)には重点的に実施。
- ドローンや地上カメラで巡回点検記録を残すと保険対応時に有利です。
2. 難燃性の防草シートの敷設
- 市販の防草シートには可燃性の製品も多く、火災対策にはなりません。
- 必ず**「JIS A 1323準拠」などの難燃性能表示付き**のシートを使用。
- PCSから半径1.5m以上を目安に全面敷設。
- シートの上に砕石を重ね敷きすると、耐久性・防火性がさらに向上。
3. 砕石・砂利の敷設
- 難燃シートとセットで、5cm以上の厚みで砕石(6号砕石等)を敷設。
- 可燃物の侵入防止、排水改善、防泥・草抑制に効果的。
- 雑草が石の間から生えてきた場合も、熱を持ちにくく着火リスクが大幅減。
4. 防火隔壁の設置(必要に応じて)
- PCSの密集地帯や、隣接する設備・敷地がある場合は鋼板・コンクリート板等の遮熱・防火隔壁を設置。
- 風による火の回り込みや延焼を物理的に遮断。
- 太陽光架台とPCSの距離が近い場合にも有効。
5. 配線・端子の絶縁劣化チェック
- 枯草に火がつく原因のひとつが、劣化したケーブルからのスパーク。
- 年1回以上の絶縁抵抗測定、端子部の目視点検を推奨。
- スパークを検知できる漏電監視装置や温度センサーの導入も有効。
6. 火災リスク対応マニュアルの整備
- O&M業者とともに、「PCS発火→延焼」の流れを想定した初動対応マニュアルを作成。
- 地元消防と連携し、消火器配置場所・通報連絡ルートの明示を行う。
7. 写真記録の保存と証跡管理
- 以下の写真を最低でも半年ごとに記録保管:
- 枯草除去後のPCS周囲写真(四方)
- 難燃防草シートの製品ラベル
- シート敷設状況と点検作業員の作業写真
- 日付入りでクラウド保存しておくと、保険会社・行政調査時にも安心。