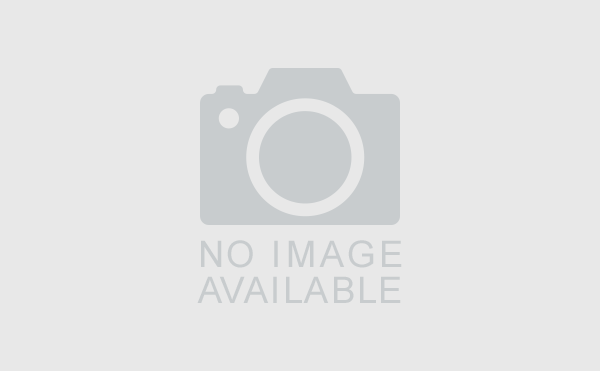再生可能エネルギーと出力抑制の不平等――国民の資産が奪われるとき
2025年現在、日本の電力インフラの一角を担っている再生可能エネルギー、とりわけ太陽光発電の現場で深刻な問題が起きている。制度上は「全量買い取り」とされた再エネ電力が、日々「出力抑制」という名のもとに買い取られず、売電収入が失われている。とりわけその煽りを最も強く受けているのが、地方に点在する日本人個人や小規模事業者が設置・運営してきた発電所である。この事実は、単なる技術的問題ではなく、エネルギーの主権と国富の帰属をめぐる重大な構造的問題をはらんでいる。
2012年のFIT(固定価格買取制度)の導入は、再エネへの投資を促す画期的な仕組みだった。再エネ発電所を設置すれば、国が定めた価格で20年間安定的に電力会社に売電できるという内容で、土地を活用したい農家や、副業を模索する地方の中小企業、そして年金不安を抱える個人投資家まで、多くの日本人が太陽光発電に参入した。民主党政権が40円という馬鹿高い買取価格を設定してしまったが、本来は単に金儲けの手段ではなく、地域にエネルギーの自立をもたらし、国のエネルギー安全保障に寄与する、まさに「地産地消の国民的取り組み」でもあったはずです。
ところが、その再エネ発電所がいま、「出力抑制」という手法によって事実上の稼働停止を命じられている。出力抑制とは、太陽が照っているにもかかわらず、電力の供給が需要を上回ると判断され、電力会社が「その時間帯は発電を止めてください」と命令することである。発電はしているが、売電できない。つまり、収入がゼロになる。
表向きの理由は「電力系統への接続順」。先に系統に接続した発電所ほど不利になる、という逆転現象が起きている。しかし現実には、外資のメガソーラーは資本力を武器に、設備投資の規模や交渉力で実質的な優先接続権を得ているケースもあり、日本人が長年かけて支えてきた発電事業が今、システムの片隅に追いやられている。
とりわけ問題なのが、これらの大規模発電所の多くが中国をはじめとする外国資本によって所有されているという事実である。日本では土地に対する外資規制がほとんどなく、山林や農地を法人名義で取得することも可能だ。さらに法人の株主や経営実態に関する情報開示も限定的で、実際には中国本土の企業が出資し、日本人名義の法人を通じて再エネ事業を展開しているという例が確認されている。
このような構図のなかで出力抑制が進められているのは、日本人事業者にとってまさに二重の不条理である。一つは、国家が定めた制度のもとで事業を始めたにもかかわらず、途中で突然「買い取りできません」と言われること。もう一つは、その抑制原因が外国資本による大規模発電所のために強行されているということだ。地産地消という発想でd制度としての運用、設計ミスでは済まされない不条理がある。
この問題は、「市場原理」で片づけられるものではない。電力というインフラは、いざというときの災害対応や国防にも関わる、安全保障上の戦略資源である。にもかかわらず、そのインフラの所有権が外国資本に奪われ、しかも地元の日本人事業者が制度運用の犠牲になっている。これを「自由経済だから仕方ない」で済ませるのは、国家の統制権放棄に等しい。
ここで問いたいのは、電力という「公共財」を、国民のために守る気がこの国にはあるのか、という一点に尽きる。今FIT制度は本来、国民から集めた再エネ賦課金によって運営されている。つまり、その原資は国民が毎月支払っている電気代の中にある。にもかかわらず、その制度で生まれた利益が外国に流れているとすれば、それは国民から集めたカネで外国を儲けさせているという構図になってしまう。
このままでは、再エネを支えてきた個人投資家や農家、地方の小企業は「見捨てられた世代」として撤退していく。設備は残っても、次世代に引き継がれることはなくなり、結果的に再エネの主導権は外国資本に握られることになる。これを再エネ推進と呼ぶのか?エネルギーの地産地消を掲げたはずの国が、その果実を海外に奪われていく現実に、誰も声を上げないのは異常だ。
我々は今こそ、出力抑制の適用方法を見直し、日本人が設置・運営してきた発電所を守る明確なルールを制度に組み込むべきである。具体的には、外資比率が一定以上の発電所には優先的に出力抑制を適用する、または地域雇用や地元自治体との連携実績を評価して、抑制対象外とするなど、制度に「国民保護の原則」を反映させることが必要だ。
再エネの未来は、市場の論理だけで動かすべきではない。その点は民主党の考え方は正しい。それは、国家の骨格であり、国民生活と安全保障に直結するテーマであるからだ。今のように、「誰が発電しているか」を問わず、機械的に抑制し続ければ、日本人はエネルギーからも、収益からも、未来からも切り離されてしまう。
国民が支えてきた制度であるならば、国民が報われる制度でなければならない。またFIT終了後も外資は施設を放置して帰国する可能性が高い。火災につながる可能性がある。この当然の道理を、もう一度取り戻さなければならない時が来ている。
2012年のFIT(固定価格買取制度)の導入は、再エネへの投資を促す画期的な仕組みだった。再エネ発電所を設置すれば、国が定めた価格で20年間安定的に電力会社に売電できるという内容で、土地を活用したい農家や、副業を模索する地方の中小企業、そして年金不安を抱える個人投資家まで、多くの日本人が太陽光発電に参入した。民主党政権が40円という馬鹿高い買取価格を設定してしまったが、本来は単に金儲けの手段ではなく、地域にエネルギーの自立をもたらし、国のエネルギー安全保障に寄与する、まさに「地産地消の国民的取り組み」でもあったはずです。
ところが、その再エネ発電所がいま、「出力抑制」という手法によって事実上の稼働停止を命じられている。出力抑制とは、太陽が照っているにもかかわらず、電力の供給が需要を上回ると判断され、電力会社が「その時間帯は発電を止めてください」と命令することである。発電はしているが、売電できない。つまり、収入がゼロになる。
表向きの理由は「電力系統への接続順」。先に系統に接続した発電所ほど不利になる、という逆転現象が起きている。しかし現実には、外資のメガソーラーは資本力を武器に、設備投資の規模や交渉力で実質的な優先接続権を得ているケースもあり、日本人が長年かけて支えてきた発電事業が今、システムの片隅に追いやられている。
とりわけ問題なのが、これらの大規模発電所の多くが中国をはじめとする外国資本によって所有されているという事実である。日本では土地に対する外資規制がほとんどなく、山林や農地を法人名義で取得することも可能だ。さらに法人の株主や経営実態に関する情報開示も限定的で、実際には中国本土の企業が出資し、日本人名義の法人を通じて再エネ事業を展開しているという例が確認されている。
このような構図のなかで出力抑制が進められているのは、日本人事業者にとってまさに二重の不条理である。一つは、国家が定めた制度のもとで事業を始めたにもかかわらず、途中で突然「買い取りできません」と言われること。もう一つは、その抑制原因が外国資本による大規模発電所のために強行されているということだ。地産地消という発想でd制度としての運用、設計ミスでは済まされない不条理がある。
この問題は、「市場原理」で片づけられるものではない。電力というインフラは、いざというときの災害対応や国防にも関わる、安全保障上の戦略資源である。にもかかわらず、そのインフラの所有権が外国資本に奪われ、しかも地元の日本人事業者が制度運用の犠牲になっている。これを「自由経済だから仕方ない」で済ませるのは、国家の統制権放棄に等しい。
ここで問いたいのは、電力という「公共財」を、国民のために守る気がこの国にはあるのか、という一点に尽きる。今FIT制度は本来、国民から集めた再エネ賦課金によって運営されている。つまり、その原資は国民が毎月支払っている電気代の中にある。にもかかわらず、その制度で生まれた利益が外国に流れているとすれば、それは国民から集めたカネで外国を儲けさせているという構図になってしまう。
このままでは、再エネを支えてきた個人投資家や農家、地方の小企業は「見捨てられた世代」として撤退していく。設備は残っても、次世代に引き継がれることはなくなり、結果的に再エネの主導権は外国資本に握られることになる。これを再エネ推進と呼ぶのか?エネルギーの地産地消を掲げたはずの国が、その果実を海外に奪われていく現実に、誰も声を上げないのは異常だ。
我々は今こそ、出力抑制の適用方法を見直し、日本人が設置・運営してきた発電所を守る明確なルールを制度に組み込むべきである。具体的には、外資比率が一定以上の発電所には優先的に出力抑制を適用する、または地域雇用や地元自治体との連携実績を評価して、抑制対象外とするなど、制度に「国民保護の原則」を反映させることが必要だ。
再エネの未来は、市場の論理だけで動かすべきではない。その点は民主党の考え方は正しい。それは、国家の骨格であり、国民生活と安全保障に直結するテーマであるからだ。今のように、「誰が発電しているか」を問わず、機械的に抑制し続ければ、日本人はエネルギーからも、収益からも、未来からも切り離されてしまう。
国民が支えてきた制度であるならば、国民が報われる制度でなければならない。またFIT終了後も外資は施設を放置して帰国する可能性が高い。火災につながる可能性がある。この当然の道理を、もう一度取り戻さなければならない時が来ている。