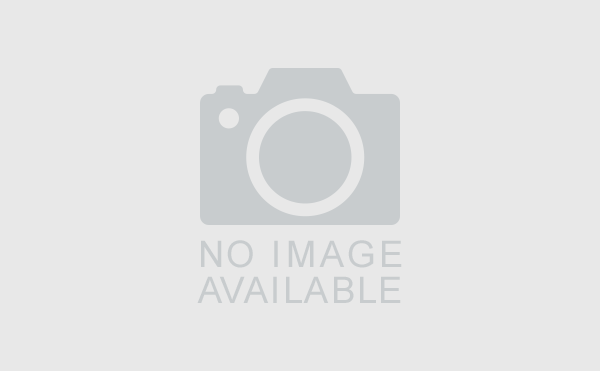ペロブスカイトに未来の地図を透かす
夕暮れの校庭を歩きながら、ふと屋根の上を見上げると、黒いパネルが静かに西日の色を吸い込んでいました。電気は目に見えないけれど、ものづくりの質は不思議と風景に滲みます。だから私は、やっぱり日本製のパネルが好きです。値札だけでは測れない設計の丁寧さ、部品一つひとつの追い込み、そして長い梅雨と猛暑、塩害と台風が混ざった“日本の天気のクセ”を身体で知っている図面の強さ——この「気候適応の作法」は、カタログでは書ききれない安心につながります。
低圧や小規模高圧の現場に行くと、その差はなおさらはっきりする。架台の寸法、裏配線の逃がし方、雨の道筋を先に決めておく下地づくり。のちのちの除草や点検、熱だまり、風鳴り、コネクタの緩み……現場の“細部”は発電量に直結します。総じてこの「細部の積み木」が堅く、経年でじわじわ効いてくる。分散型の小さな発電所ほど、こういう基礎体力が効率の差(=kWh単価の差)になって表れるのです。
そして、近ごろ私がいちばん期待しているのがペロブスカイト。軽くて、曲げられて、低照度にも強く、建物の壁や窓、屋根材そのものへと“しみ込む”ように実装できる。大げさな造成をせず、既存の街並みをそのまま発電所に変えていける発想は、まさに日本向きです。学校の屋上、物流倉庫の大屋根、駅ビルのカーテンウォール、商店街のアーケード、農業ハウスのトップライト……メガソーラーのために山を削らなくても、都市と生活空間の内側で静かにkWhを積み増せる。分散と調和の国らしい、やさしい増え方ができるのが良い。
もちろん、夢だけで語るつもりはありません。ペロブスカイトは耐久が勝負です。湿気・熱・紫外線・機械荷重にどこまで耐えるか。封止材や層構成、電極、配線の腐食……「85℃・85%」のような加速試験の壁を地道に超えて、製品寿命と保証の“言葉”を固めなければ、市場は本気になりません。だからこそ、ここは積極財政の出番だと思うのです。安全性と信頼性の規格づくり、公共建築や学校・病院での段階的な実証、リサイクルと責任ある調達の仕組み、そして量産ライン(ロール・ツー・ロール等)への初期投資。国がボトルネック(規格・実証・量産)にお金を入れて産業の“筋肉”を作れば、民間は自信を持って走り出せる。補助金で赤字案件を救うのではなく、国産の土台を太くして、総コストの底を下げにいくのが筋です。
分散型との相性も抜群です。軽いペロブスカイトは、既存の屋根に無理のない荷重で乗る。施工時間が短く、足場の手間も小さく、更新(リパワリング)も傷を浅く重ねられる。系統の側から見ても、需要地直結で配電レベルに馴染み、出力抑制に巻き込まれにくい。非常時には蓄電池と組んでマイクログリッドの核になれる。小さな単位が無数に灯る——この国に似合う電気の増やし方です。
メガソーラーの大舞台は、どうしても「遠く・大きく・一気に」になりやすい。系統は混み、送電の道は長く、天気の機嫌が悪い日は丸ごと止まる。造成の大工事は土砂と水の流れを変え、地域と心が離れる。コストは資材と為替と金利の波に揺さぶられ、警備と保険は年々かさむ。私は、国民に静かに回ってくる電気料金の領収書を思うと、やはり足はそちらへ向かないのです。
一方で、日本製+分散は「近く・小さく・重ねて」ゆく道。屋根と壁を発電面に変え、駐車場に日陰をつくり、工場のコストを下げ、学校に学びの教材を置く。地域の電気が地域の暮らしに還流する。ペロブスカイトは、その景色をぐっと現実に引き寄せる鍵でしょう。軽やかに、静かに、しかし確実にkWhを増やす——そんな増え方を、私は日本に似合うと感じています。
国としては、送電網・蓄電・周波数調整という“電力の道路”に先に投資して、原子力の安全最優先の再稼働・更新と高効率LNGの安定運用で土台を固める。その上で、日本製の屋根・壁・駐車場に分散させ、ペロブスカイトの量産・規格・実証を国家プロジェクトで押し上げる。補助ではなく規格と市場、救済ではなく国産の筋肉。これが、保守としての責任と、積極財政の正しい使い道だと思うのです。
夜、街の灯がぽつぽつと点いていく。あの一灯一灯の裏側に、どこのだれがつくった素子と、どこの工場の封止膜と、どこの町工場の架台ボルトがいるのか——想像してみると、同じ電気でも少し温度が変わって見えます。日本の手触りをまとったパネルで、分散した小さな発電所を、静かに増やしていく。メガの眩しさに頼らず、暮らしの隙間に灯りを足していく。そんな“しぶとく強い”増やし方で、私たちの家計と産業を守りたい。ペロブスカイトの薄い一枚に、そんな未来の地図を透かし見ながら。