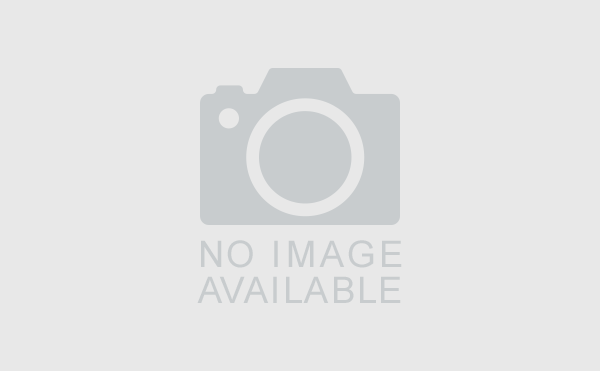【発電量が落ちた気がする?】太陽光オーナーがまず確認すべき6つのステップ
「最近、なんか発電量が落ちてるような気がするんです…」
これ、太陽光発電をやってると誰しも一度は感じる疑問ではないでしょうか。
でもちゃんと確認すれば、原因は必ず見つかります。
そんなときに何をどの順番で確認すべきか、初心者の方でもわかるように、ステップごとに説します!
ステップ①:「気がする」はまだ感覚。まずはデータで確認しよう
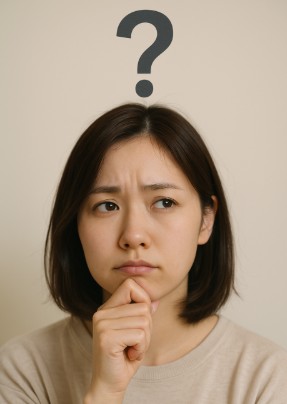
最初にやること。それは仮説を立てる材料を集めることです。
つまり、今の段階では「発電量が減った気がする」だけで、まだ本当に問題があるかはわかりません。
では、なにが原因の候補になりうるかというと──
- パネルの故障
- パワコン(PCS)の異常
- 日射不足(天気の影響)
- 電力会社の出力抑制(代理制御)
- ケーブルの断線や盗難
ざっとこれくらいあります。けっこう幅広いですよね。
ということで、最初にやるべきは「パワコンごとの発電データをチェックすること」です。
ステップ②:まずはパワコンごとの出力を見てみよう

監視装置(モニタリングシステム)がついている発電所なら、パワコン(PCS)ごとの出力グラフやログを見てみましょう。すると、こんな風に見えてくるかもしれません。
「あれ、この1台だけ明らかに出力が低いぞ…?」
「このパワコンだけ半分くらいしか発電してない」
こういう差があれば、まずそのパワコンに何かありそうだなとアタリをつけられます。
ステップ③:パネルの異常をチェックしてみる

パワコンの次に疑うべきはパネルの不具合です。
とくに古い発電所や、FIT初期(2012〜2015年)に建てた人は要注意。当時は安かろう悪かろうのメーカーも混ざってました。
検査には「パネルテスター」などの検査機器を使います。これでパネル1枚ずつの健全性を測れます。
もしここで「全部問題なし」と出たら、パネルが原因の可能性を消せるわけですね。
※ちなみに、パネルメーカーがすでに廃業していると、保証は使えません…自費修理コースです(泣)
ステップ④:パワコンの個別出力を現場で確認!
私のつたない経験上、一番壊れやすいのはパワコンです。
しかも厄介なのが「エラーを出さずに壊れることがある」ってこと。
たとえば、田淵電機のパワコンなんかだと、回路(ストリング)単位で壊れていてもエラーコードが出ないこともあります。
【パワコン確認の流れ】
- パワコンのカバーを開ける
- モニタを「出力表示モード」に
- 晴れていれば10kW前後の表示があるはず
- もし8kWとかだったら「おや?」と思うべき
- パワコンのブレーカー(回路)を1つずつOFFにして、出力の変化を見ていく
もしスイッチを切っても出力がまったく変わらない回路があったら、それはそもそも発電していない=故障しているということです。
ステップ⑤:ケーブル・コネクタの断線や不具合
意外と多いのがこれです。
- 雨風でケーブルが腐食
- 動物にかじられた
- 盗難や断線
- MC4コネクタの接触不良
こんなトラブルがあると、その回路は丸ごと発電しなくなります。
ここで使える便利アイテムが「クランプ式の電圧・電流計」。
ストリングごとに流れてる電流がゼロなら、そこが不発とわかります。
ステップ⑥:すべて正常…なのに発電量が低いとき
ここまでで、
- パネル:正常
- パワコン:正常
- ケーブル:正常
だったら、次に考えるのは**「外的要因」**です。
① 日射量の減少
これはよくある話です。
特に冬場や黄砂が多かった年、雨が続いた地域では日射量が落ちます。
気象庁の「過去の気象データ」で、前年と比較するとわかりやすいです。
② 出力抑制(代理制御)
最近特に増えているのがこの代理制御。
東北電力、中部電力など一部エリアで、電力系統の都合で発電が制限されるケースがあります。
対策:抑制対応の設備導入を検討しよう
もし「代理制御」が頻発しているなら、長期的には対策機器の導入も選択肢に入ってきます。
- 抑制対応型のパワコン
- 抑制情報を受けられるRAU(制御ユニット)
こういった設備を入れることで、無駄にロスする発電を減らすことが可能です。
私自身も今このアップグレード作業を準備中です。資金はかかりますが、将来の安定収益のためには投資の一つですね。
まとめ:発電低下が気になったらこの順番でチェック!
- 感覚じゃなくデータで確認(監視グラフなど)
- パワコンごとの発電量をチェック
- パネルの健全性を検査
- パワコンの個別出力を現場で確認
- ケーブルやコネクタの断線を確認
- それでもダメなら日射or代理制御を疑う
最後に一言…
太陽光発電って「メンテナンスフリー」って言われがちですが、実際はちゃんと見てあげないといけない設備なんです。
でも逆に言えば、こうしてチェックポイントさえ押さえておけば、
「なんとなく減ってる気がする」を「こういう理由でした」とハッキリさせられる。
発電量が下がったかな?と感じたら、ぜひ今回のチェックリストを参考にしてみてくださいね!
太陽光発電の発電量が落ちたときのチェックリスト
【ステップ1】感覚ではなくデータで確認!
□監視システム(モニタリング)の発電量グラフを確認
□パワコン(PCS)ごとの出力にばらつきがないかを見る
□前年・前月と比べて明らかに発電量が低いか確認
【ステップ2】パワコンごとの発電量をチェック
□パワコンごとの出力を確認(1台だけ出力が低くないか?)
□ログや履歴グラフで過去との比較も見る
□出力が低いパワコンにアタリをつける
【ステップ3】パネルの健全性を検査(必要なら業者依頼)
□パネルチェッカーでストリングごとに測定
□パネルの劣化やホットスポットがないか確認
□メーカーが存続しているか?(保証の有無に関わる)
【ステップ4】パワコン現地チェック(晴天時がおすすめ)
□パワコンのカバーを開け、出力モードに切替
□出力が10kW前後あるか確認(晴天時)
□ブレーカーを1つずつOFFにして差分を確認
□OFFにしても出力が下がらない → その回路が発電していない
□エラーコードが出ていないか確認(※出ない場合もある)
【ステップ5】配線や接続不良を確認
□ケーブルの断線、動物被害、腐食などを目視でチェック
□MC4コネクタに緩み・腐食・熱融解がないか確認
□クランプ式電圧・電流計で各ストリングの電流を測定
□電流ゼロのストリングがあれば要点検
【ステップ6】設備に異常がなければ「外的要因」を疑う
□気象庁などで「日射量」の過去データと比較
□冬季や梅雨時期、黄砂などの影響も確認
□電力会社の「出力抑制(代理制御)」情報を確認
□代理制御通知メール・Webサイトの通知履歴を確認
【ステップ7】必要なら設備のアップグレード検討
□抑制対応型パワコンの導入を検討
□抑制制御ユニット(RAUなど)の導入を検討
□資金計画を立て、必要経費を見積もり
□FIT期間中の損失を抑える投資として判断
備考欄
- 検査日:
- 検査担当者:
- 気になった点・改善点メモ: