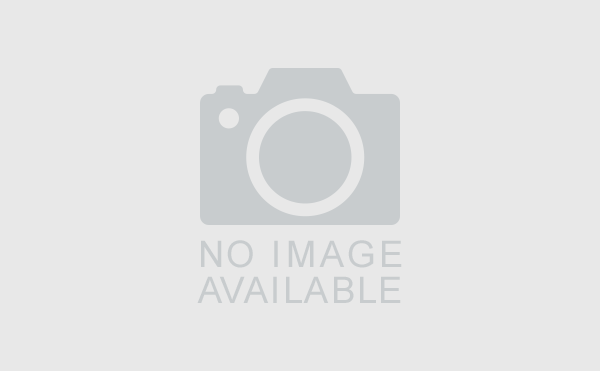「再エネ発電」が苦境 発電所の倒産、過去最多 2024年度 帝国データバンク

再生可能エネルギーを中心とした発電事業者の倒産や廃業が相次いでいる。2024年度(2024年4月~2025年3月)に発生した、太陽光発電や木質バイオマス発電など再エネを中心とした発電事業者の倒産(負債1000万円以上、法的整理)は8件となり、前年度から倍増した。休廃業・解散(廃業)の44件を合わせると、過去最多となる52件が市場から消滅した。
ご参照に https://news.yahoo.co.jp/articles/232f8d434e61748956a5fda5abbda47733e19d65
私が思うに、再エネ倒産の本質は無謀なメガソーラー開発の構造リスクにある。
2024年に入り、帝国データバンクが報じた再エネ発電関連企業の倒産件数が過去最多となった件について、多くの報道や論評が「再エネ事業そのものの危機」や「発電事業者の経営難」と結びつけていますが、この分析には大きな誤解があります。
本件の中心にあるのは、高圧や特高を扱うメガソーラー開発業者(いわゆるデベロッパー)です。彼らが破綻に至った最大の理由は、以下のような構造的な問題にあります。
倒産の主因は「計画の甘さ」と「開発至上主義」
開発業者の多くは、運転開始までに数年単位を要するにもかかわらず、実現性の精査をせずに用地だけを先行確保し、事業収益モデルが極めて曖昧なまま資金調達や土地契約を進めていました。その結果、いわば「土地の山」を抱えながら、工事着手にも至らず資金繰りが尽きて倒産に至ったのです。たとえば、全国に8万ha以上の用地を確保していた企業が破産した背景には、用地取得だけが進み、FIT買取単価の減額リスクや許認可のハードルを甘く見積もっていたことがあります。収益化の目処が立たない中、用地費用や人件費などのキャッシュアウトだけが続き、資金破綻を招いたのです。
FITの高額権利が“腐っていった”実態
さらに重要なのは、これらのデベロッパーが多く保有していた30円〜40円といった旧来の高額FIT権利が、開発の遅れにより無効化あるいは減額されたという点です。
制度変更により、当初想定していた高利回りの買取価格が18円、15円、あるいはそれ以下に引き下げられ、プロジェクト全体の収益構造が崩壊。
多くの開発業者がこの「FITの価値毀損」に対応できず、結果として事業を畳むことになったのです。
この記事で問題なのは、こうした破綻案件であって、高額FITがなくなっているにも関わらず一度認定されたFIT案件であれば賦課金の中に組み込まれてしまっているという日本の制度の構造です。つまり、実際に売電する可能性がない、もしくは事業化すらされていない案件に対しても、制度的に費用の一部が上乗せされてしまっていることです。
これは制度の設計ミスであり、「再エネ=非効率・コスト高」といった誤解を国民に与える大きな要因にもなっています。
再エネ全体の問題ではなく、“制度を歪めた開発至上主義”の失敗
今回の倒産増加は、太陽光発電事業そのものの不振を意味するものではありません。むしろ、「用地取得+FIT権利転売」を目的とした一部の投機的開発業者の行き詰まりが表面化しただけであり、これは当然の淘汰とも言えます。
今後必要なのは、FIT制度の本来の趣旨である「発電の実現」と「地域への還元」を前提とした、実行可能性の高い開発評価と厳格なモニタリング体制の構築です。
そして何より、国民から不要な賦課金を徴収しようとする財務省の思惑を阻止し、これ以上の負担増を食い止めることが重要です。
今回の記事は、表面的には再エネ業界の苦境を伝えているように見えますが、実際には「太陽光は儲からないから賦課金が上がる」と一般読者に印象付けようとする“深い誘導”が潜んでいます。
しかし、現実には計画性のない開発や不誠実な事業者による破綻が問題の本質であり、健全に発電を続けている事業者や、それを日々支えるメンテナンス業者までが「同じ穴のムジナ」と見なされてしまうのは、明らかに誤りです。
だからこそ、FIT制度の透明化と構造の見直しが、再エネの信頼回復に向けて必要不可欠なのです。